
相撲の起源と歴史
相撲は日本古来の伝統スポーツとして知られ、その歴史は非常に古く、神話の時代にまで遡ることができます。古代の日本では、力比べが神事として行われていた記録が残っています。ここでは、相撲の始まりから現代に至るまでの変遷を詳しく探っていきます。
神話時代と古代の力比べ
相撲の起源は、日本神話に登場する「建御雷神(タケミカヅチ)と建御名方神(タケミナカタ)の力比べ」に由来するとされています。この神話では、天孫降臨の際に二人の神が国譲りのために相撲を取ったとされ、これが相撲の原型と考えられています。古事記や日本書紀などの文献に記述されており、相撲は単なる競技ではなく、神聖な儀式として位置づけられていたのです。 奈良時代に入ると、宮廷行事として「相撲節会」が開催されるようになりました。これは天皇の前で力士たちが技を競うもので、収穫祭や祈祷の意味合いが強かったです。平安時代には貴族社会で人気を博し、武士の台頭とともに軍事訓練の一環としても取り入れられました。たとえば、源氏物語にも相撲の描写が見られ、当時の文化に深く根付いていたことがわかります。また、古代の相撲は土俵がなく、地面に直接線を引いて行われ、ルールも今ほど厳格ではありませんでした。力士たちは裸に近い姿で戦い、勝敗は投げや押し出しだけでなく、相手を倒すこと全般でした。この時代、相撲は娯楽を超えて、国家の安寧を祈る宗教的な側面を持っていたため、多くの寺社で奉納相撲が行われました。たとえば、出雲大社や厳島神社での相撲は今も伝統として残っています。こうした背景から、相撲は日本の精神文化を象徴するものとして発展してきたのです。時代が進むにつれ、相撲は民間にも広がり、村祭りでの力比べが一般的になりました。これにより、プロの力士が生まれる基盤が整いました。
江戸時代からの職業化と近代化
江戸時代になると、相撲は大衆娯楽として爆発的に人気を博しました。寺社奉納相撲から興行相撲へ移行し、江戸や大阪で常設の相撲小屋が建てられました。この時期に「横綱」という最高位が確立され、吉田司家が免許を授与する制度が生まれました。 著名な力士として雷電為右衛門がおり、彼の強さは伝説的で、生涯成績は254勝8敗という驚異的な記録を残しています。明治維新後、西洋文化の影響で一時衰退しましたが、1909年に日本相撲協会が設立され、プロスポーツとして組織化されました。両国国技館の建設(1909年)により、本格的な会場が整い、興行が安定しました。大正・昭和初期には双葉山定次のような不世出の強豪が登場し、相撲ブームを起こしました。戦後、テレビ中継の開始(1953年)で全国的な人気を獲得し、国際的にも注目されるようになりました。現在では、年間6場所の本場所が開催され、力士たちは厳しい階級制度の中で戦っています。歴史を通じて、相撲は神事から娯楽、プロスポーツへと進化し、日本人のアイデンティティを体現する存在となっています。たとえば、外国人力士の増加(1990年代以降)はグローバル化を象徴し、ハワイ出身の小錦やモンゴル出身の白鵬が横綱に昇進したことは大きな話題となりました。このように、相撲の歴史は日本の社会変遷を映す鏡なのです。
相撲の基本ルール
相撲のルールはシンプルに見えますが、細かな規定が多く、公平性を保つために厳格に運用されています。試合は短時間で決着がつくため、瞬時の判断が重要です。以下では、ルールの概要と詳細を解説します。
土俵と試合の開始方法
相撲の試合は直径4.55メートルの円形の土俵で行われます。土俵は粘土で作られ、表面に土を敷き、俵で縁取られています。力士は土俵外に出るか、触れる部分が地面につくと負けとなります。 試合開始は「仕切り」で、両者が蹲踞の姿勢から睨み合い、タイミングを合わせてぶつかります。行司が軍配を振るうタイミングで本気の攻防が始まりますが、偽りの仕切り(立ち合い不備)でやり直しになる場合もあります。基本的に禁止事項として、髪を引っ張る、目をつく、拳で殴るなどの行為は反則です。勝ち方は「力士の体の一部が土俵外に出る」「足の裏以外が土につく」の2点が主で、83手の決まり手があります。たとえば、寄り切り(押し出す)、上手投げ(投げる)などです。試合時間は無制限ですが、平均4秒程度と非常に短いです。水入り(休憩)は長引く場合に認められ、力士の体調を考慮します。また、土俵上での塩まきは邪気を払う神事的な意味があり、1試合に数回行われます。このルールは日本相撲協会の規則書に詳細に定められており、毎年微調整が行われています。初心者には難しく見えますが、基本は力と技のぶつかり合いです。
反則と決まり手の種類
反則は8つあり、違反すると即負けとなります。たとえば、両手で相手の喉を突く「突き指」や、土俵外から攻撃する行為です。決まり手は非技を含む83種類で、投げ技、押し技、掛け技などに分類されます。 非技とは、反則や棄権による勝ちを指します。行司は勝敗を判断し、物言いがつけば協議します。ビデオ判定は導入されていませんが、目視と経験で公正さが保たれています。力士の階級によって取り組み数が異なり、幕内は1日1番、十枚目以下は複数番です。ルールの厳格さは相撲の伝統を守るために重要で、たとえば女性の土俵入り禁止は議論を呼んでいますが、文化的な理由からです。このように、ルールは競技の公平性と安全を確保しつつ、神聖さを保っています。詳細を知ることで、試合観戦がより楽しくなります。
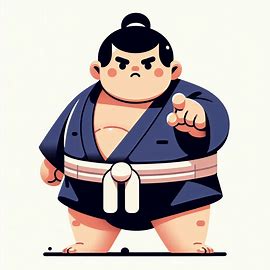
土俵と力士の装備
相撲の舞台である土俵と、力士の身につけるものはすべて意味があり、伝統を象徴しています。これらを理解することで、相撲の奥深さがわかります。土俵は単なる競技場ではなく、神聖な空間として扱われ、力士の装備も機能性と儀式性を兼ね備えています。古来から受け継がれたこれらの要素は、相撲が日本文化の重要な一部であることを示しています。たとえば、土俵の構造一つ取ってみても、古代の神事から派生したものが多く、現代のプロ相撲でも厳格に守られています。また、力士のまわしは戦いの道具でありながら、美しいデザインで観客を魅了します。この章では、そんな土俵と装備の詳細を深く掘り下げていきましょう。
土俵の構造と意義
相撲の土俵は、単なる円形のリングではなく、深い宗教的・文化的な意味を持つ聖域です。直径は4.55メートル(15尺)で、高さは約0.34メートルから0.6メートル程度と定められています。このサイズは江戸時代からほぼ変わらず、力士二人が十分に動き回れる広さを確保しつつ、観客に迫力ある試合を提供するよう設計されています。土俵の材料は主に粘土質の土で、表面には細かい砂状の土が撒かれ、滑りにくくしています。縁は稻俵(いなわらで作った俵)を22本使用して円を描き、これが土俵の境界線となります。俵の数は陰陽道の影響を受け、奇数であることで魔除けの意味があると言われています。土俵は神が降臨する場所として、女性の立ち入りが禁じられています。 この禁忌は、土俵が神聖視されるためで、社会的な議論を呼ぶこともありますが、伝統を守る姿勢は変わりません。土俵の中央には「蛇の目」と呼ばれる二つの白い線が引かれ、力士の仕切り位置を示します。また、土俵の上には「屋根」がかけられ、これは神社鳥居を模したもので、四本の柱に支えられています。柱の色は東が青、西が白、南が赤、北が黒と四神にちなみ、相撲の神事性を強調します。土俵の建設は専門の職人「土俵大夫」が担い、場所前に新しく作り直されます。地下には清めの塩や酒、米などが埋められ、邪気を払う儀式が行われます。この習慣は古事記に遡る神話から来ており、相撲が豊作祈願だった時代を思い起こさせます。試合中、力士は土俵に入る前に塩をまき、浄化の意味を込めます。一日に数十キロの塩が消費されることもあります。土俵の意義は競技を超え、日本人の自然崇拝を体現しています。たとえば、本場所の国技館では土俵がよく見えるよう設計され、照明も柔らかです。地方場所では仮設土俵が作られ、土を運び込む作業が必要です。力士にとって土俵は命の舞台であり、血が落ちた際の「土俵祓い」は厳粛です。現代では安全性を高めるため、土の硬さ調整が行われ、力士の健康を守っています。
まわしと化粧まわしの役割
力士の装備で最も象徴的なのが「まわし」です。これは長さ約9メートル、幅0.6メートルの絹布を腰に巻いた帯で、試合中の抓り所となります。素材は絹が主流で、重さは約4キログラムもあり、締め付けが強すぎると呼吸に影響します。まわしは白と黒が基本ですが、部屋ごとの色分けがあり、伝統を表します。化粧まわしは番付上位者の儀式用で、豪華な刺繍が入り、数百万の価値があります。 通常のまわしは稽古用で耐久性を重視しますが、本場所用は光沢が美しく、威厳を高めます。巻き方は四つに折って行い、緩むと反則になるため、世話人が手伝います。まわしの歴史は平安時代の褌形式から江戸時代に進化しました。機能的には相手を投げる支点となり、力の伝達を助けます。裸に近い姿は神への奉納を意味します。化粧まわしは幕内力士以上が土俵入りで着用し、金糸の刺繍が入ります。デザインは部屋の紋章や故郷のモチーフが多く、制作費は数百万円かかります。役割は儀式的なもので、観客に披露され、ステータスを象徴します。ほかに、髪は大銀杏髷に結われ、試合中崩れにくいよう固めます。装備全体として、安全面ではまわしの調整が重要です。
力士の階級制度
相撲界は厳しいピラミッド構造で成り立っており、力士たちは日々の成績によって昇進や降格を繰り返します。この階級制度は、力士たちのモチベーションを高め、競争を促進する重要な仕組みです。相撲がプロスポーツとして成立している基盤であり、伝統的な番付表に記される位は力士の名誉と生活を左右します。たとえば、入門した新弟子から最高位の横綱まで、長い道のりを歩む過程で多くのドラマが生まれます。この章では、そんな階級制度の詳細を深く探ります。階級の違いによる待遇の差や、昇降格の厳しさを知ることで、力士たちの努力がよりリアルに感じられるでしょう。歴史的に見ても、江戸時代から始まったこの制度は、現代まで進化を続けています。年間6場所の成績がすべてを決めるため、1番1番の重みが大きいのです。
十両以上と幕下以下の違い
相撲の階級は大きく分けて、関取と呼ばれる十両以上と、それ以下の幕下以下に二分されます。まず、十両以上はプロ力士のエリート層で、幕内(まくうち)と十両の2つのカテゴリがあります。幕内はさらに横綱、大関、関脇、小結、前頭と細分化され、最上位の横綱は生涯位で降格がありません。横綱は生涯位で、降格なしの最高栄誉です。 これらの力士は日本相撲協会から給与が支給され、十両以上になると「関取」の称号を得て、化粧まわしを着用したり、専属の付き人を雇ったりする特権が与えられます。給与は階級により異なり、横綱は月額約300万円、大関は約250万円です。また、懸賞金や場所手当などのボーナスもあり、生活が安定します。一方、幕下以下は序二段、三段目、幕下とあり、ここでは給与がなく、部屋の寮生活で月数万円の奨励金のみです。食事や稽古は部屋持ちで賄われますが、プロとしての待遇はなく、アマチュアに近い立場です。十両昇進は大きな関門で、幕下上位で7戦全勝近くの成績が必要になることが多く、「関取になる」ことは夢の第一歩です。待遇の違いは歴然で、十両以上になると個室が与えられ、結婚や外出の自由度も増します。たとえば、テレビ出演やCM契約などの副収入も可能になり、社会的地位が向上します。幕下以下は雑用が多く、関取の世話をする「付け人」として働くため、謙虚さを学ぶ場でもあります。この格差はモチベーションを生み、力士を上を目指させる原動力です。外国人力士の増加で、十両以上の国際色が豊かになりました。協会は番付編成会議で公平に決め、東西の分け方も考慮します。
昇進と降格の基準
昇進と降格は本場所の勝ち星で決まり、非常に厳格な基準が設けられています。基本的に、1場所15日間の成績で8勝7敗以上が勝ち越しで昇進の目安となりますが、階級が高くなるほど要求される成績は厳しくなります。横綱昇進は協会の推薦と実績で、慎重に審議されます。 たとえば、大関から横綱へは、2場所連続優勝かそれに準ずる成績(例: 14勝や13勝)が必要で、品格やリーダーシップも審査されます。大関昇進は関脇で2場所合計26勝以上が目安で、陥落後はすぐに復帰できる特例もありますが、失敗すると関脇へ降格です。小結や前頭は相対的な成績で変動します。降格は負け越しで即座に起こり、7勝8敗で1枚落ち、連続負け越しで急降下します。怪我による休場は考慮があり、全休でも半枚落ち程度に留まります。十両から幕下への陥落は「関取落ち」と呼ばれ、給与喪失の痛手です。基準の詳細は協会の内規で定められ、番付編成会議で議論されます。昇進の喜びは大きく、新横綱の口上は感動的です。一方、降格の悔しさは引退を促す場合もあります。近年、データ分析が取り入れられ、対戦相手の強さを考慮した調整も進んでいます。

相撲の技と戦術
相撲は単なる力のぶつかり合いではなく、洗練された技と巧妙な戦術が勝敗を分ける競技です。数百年にわたる歴史の中で蓄積された技術は、力士の個性や体型によって多様に展開され、観客を魅了します。この技と戦術の奥深さを理解することで、短い試合の中に込められたドラマがより鮮やかになります。たとえば、立ち合いの瞬間から始まる心理戦や、相手の隙を突くタイミングの妙が、相撲の真髄です。この章では、基本的な技から応用戦術までを詳しく解説します。力士たちは日々の稽古でこれらを磨き、怪我を防ぎつつ最大の効果を発揮するよう工夫しています。現代の相撲では、外国人力士の影響で新しい技も生まれ、進化を続けています。戦術は事前の相手研究に基づき、柔軟に変わるため、予測不能な展開が楽しめます。相撲の技は83手の決まり手として公式に分類され、非技を含む多さです。初心者でも基本を押さえれば観戦が深まるでしょう。歴史的に、江戸時代に技が体系化され、現代のビデオ分析でさらに洗練されています。
基本技の押しと投げ
相撲の基本技は大きく押し技と投げ技に分けられ、これらが試合の基盤となります。押し技は相手を土俵外へ押し出すもので、寄り切り、突き出し、押し出しが代表です。体重を活かした力任せのイメージが強いですが、タイミングと足運びが重要で、立ち合いから一気に間合いを詰める戦法が効果的です。立ち合いの衝突で優位を取るのが基本戦術です。 たとえば、大柄の力士は胸押しで相手を圧倒し、速い力士は突き放してバランスを崩します。この技は体力消耗が激しく、持久戦になると不利になるため、早い決着を目指します。歴史的に、雷電為右衛門のような強豪が押し技で無敵を誇りました。投げ技は抓んだまわしを活かし、上手投げ、下手投げ、掬い投げなどがあります。相手の重心をずらし、回転力を加えて土俵外へ放るのがコツで、柔軟性と握力が鍵です。立ち合いでは当たらずに抓る「引き技」から投げに移行する戦術も有効で、相手の勢いを逆手に取ります。基本技の習得は入門時の四股踏みから始まり、ぶつかり稽古で体得します。押しと投げの組み合わせ、たとえば押しで崩してから投げる連係が上級者の域です。体型による適性があり、瘦身の力士は投げを、巨漢は押しを好みます。禁じ手との境界で、髪を掴むのは反則ですが、まわし抓りは許されます。この基本をマスターすれば、力士のスタイルがわかります。現代ではモンゴル勢の投げ技が強く、日本人力士も対応を迫られています。稽古では木柱を使ったてっぽうで押しを鍛え、砂袋で投げの練習をします。戦術的に、押しは正面から、投げは横から攻める多角化が重要です。
応用技と禁じ手
応用技は基本を基にした掛け技、捻り技、反り技などで、状況に応じた柔軟さが求められます。掛け技は内掛け、外掛け、足取りで、相手の足を絡めて倒すもので、素早い動きが命です。戦術は相手の弱点を突くもので、事前の研究が鍵です。 捻り技は小手投げや掴み投げで、体を捻って崩し、意外性を活かします。反り技は豪快で、宇良のような小兵力士が大物を倒すドラマを生みます。これらの技は決まり手83手中多くを占め、非技(反則勝ちや棄権)以外で多様です。戦術面では、相手の癖をスカウトし、立ち合いの変化(張り差しや猫騙し)で混乱させます。心理戦も重要で、睨み合いや塩まきでタイミングをずらします。応用技のトレーニングは相撲部屋の申し合い稽古で、親方がアドバイスします。禁じ手は8つあり、拳殴り、髪引っ張り、目突き、喉突き、陰部蹴り、二本指差し、胸突き、腰掴みで、即反則負けです。これらは安全と公平を守るためで、江戸時代に定められました。違反は行司の判断で、物言いがつく場合もあります。応用技の進化はビデオ分析から生まれ、データで相手の勝率を計算します。たとえば、白鵬の変化技は賛否ありましたが、効果的でした。禁じ手を避けつつ、ギリギリの技を使うのがプロの腕です。
相撲部屋と生活
力士たちは相撲部屋という共同生活の場で、厳しい規律の下で鍛錬を積み重ね、人間としても成長します。この部屋システムは相撲界の基盤であり、親方や兄弟子から技や礼儀を学び、絆を深める場所です。相撲部屋は単なる住居ではなく、家族のような共同体で、入門から引退までを支えます。たとえば、新弟子は雑用から始め、番付が上がるにつれ役割が変わります。この章では、部屋の組織や日常の詳細を深く掘り下げます。力士の生活を知ることで、彼らの献身的な努力が実感でき、相撲への敬意が増すでしょう。歴史的に、江戸時代に部屋制度が確立され、現代では約40の部屋が存在します。部屋ごとの特色、たとえば九重部屋の厳しさや出羽海部屋の伝統が、力士の個性を形成します。生活は朝型で、テレビで見る華やかな試合の裏側に過酷さがあります。栄養管理や精神鍛錬も重要で、引退後の進路まで考慮されます。外国人力士の増加で、国際的な部屋文化も生まれています。相撲部屋は日本独特の師弟関係を体現する文化遺産と言えます。
部屋の組織と親方
相撲部屋は親方を頂点とした階層組織で、力士、世話人、床山、呼出、後援者で成り立っています。親方は元力士で、日本相撲協会の株を持った年寄名跡を襲名し、部屋を運営します。親方は元力士で、指導と生活管理をします。 指導は技の伝授だけでなく、生活全般を監督し、力士の結婚や金銭管理まで関与します。たとえば、九重親方(元千代の富士)は厳格な指導で知られ、多くの横綱を育てました。組織的には、部屋頭(関取上位)が親方を補佐し、兄弟子が新弟子を教育します。世話人は食事や掃除を担い、元力士が多いです。床山は髷を結い、呼出は土俵業務をします。入門時は序ノ口からで、親方のスカウトや紹介で加入します。新弟子は付け人として関取の世話し、朝の支度から夜の就寝まで従います。この師弟関係は厳しく、叱責も多いですが、信頼で結ばれます。部屋のルールは親方次第で、門限や携帯制限があり、規律を保ちます。後援会は資金援助をし、化粧まわし寄贈や激励会を開きます。部屋の規模は10人から50人以上と様々で、大部屋は競争激しく、小部屋は家族的です。親方の役割は大きく、部屋の存続がかかり、協会の監査を受けます。外国人力士が入ると、通訳や文化適応支援が必要で、多文化共生が進みます。組織の強みは縦社会で、礼儀や忍耐を教えます。たとえば、朝青龍の部屋時代はモンゴル勢の結束が強かったです。この組織を知ることで、力士のバックグラウンドがわかり、試合の背景に深みが出ます。部屋は力士の第二の家族であり、一生の絆を生むのです。
日常の鍛錬と食事
力士の日常は朝5時の起床から始まり、稽古、食事、休憩の繰り返しで、体重維持と技磨きに集中します。朝稽古は四股踏み、てっぽう、ぶつかり稽古で、2時間以上続き、汗だくになります。睡眠と栄養で体重を増やし、力の源とします。 申し合いでは実戦形式で、親方がアドバイスします。午前中は掃除や付け人業務、午後は自由時間ですが、トレーニング継続です。食事はちゃんこ鍋が中心で、1日2食、朝と夕に大量摂取し、5000~10000kcalを取ります。材料は鶏肉、魚、野菜で、タンパク質豊富、ビールでカロリーアップします。料理は下位力士の当番で、味付けの工夫が部屋の特色です。体重増加は相撲の武器で、150kg以上が標準、睡眠は午後寝で消化促進します。鍛錬は怪我防止のストレッチも含み、トレーナーがマッサージします。休日は月2回程度で、家族訪問や趣味ですが、節制を守ります。精神面では読書や座禅で集中力を養い、引退後の資格取得も奨励されます。女性力士の部屋はないが、部屋生活は男社会の厳しさを教えます。栄養管理は現代化し、サプリメント使用も増えました。この生活は過酷ですが、達成感があり、横綱になる基盤となります。食事のちゃんこはファンイベントでも人気です。

本場所と興行
相撲の本場所は年間6回開催される大イベントで、15日間にわたる熱戦が力士たちの運命を決め、ファンを沸かせます。この興行システムは相撲の華であり、伝統的な儀式と現代のエンターテイメントが融合したものです。たとえば、国技館の満員御礼の雰囲気や、テレビ中継の臨場感が相撲人気を支えています。この章では、本場所のスケジュールから観戦文化までを詳しく探ります。興行の裏側を知ることで、力士のプレッシャーや協会の運営努力がわかります。江戸時代からの興行相撲が基盤で、明治以降にプロ化され、戦後のテレビ時代で全国区になりました。現代ではインターネット配信や海外展開でグローバル化が進み、経済効果は数百億円規模です。懸賞金やチケット販売が収入源で、力士のモチベーションにもつながります。本場所は神事要素を残し、土俵入りや行司の掛け声が荘厳です。コロナ禍での無観客経験から、ファンの重要性が再認識されました。相撲はスポーツを超えた文化イベントで、家族連れから外国人観光客まで幅広い層を魅了します。以下で、スケジュールと文化の詳細を丁寧に解説していきます。
場所のスケジュールと優勝
本場所は奇数月に開催され、1月(初場所)、3月(春場所)、5月(夏場所)、7月(名古屋場所)、9月(秋場所)、11月(九州場所)の6回です。東京の両国国技館で1・5・9月、地方(大阪、名古屋、福岡)で残り3回とローテーションします。懸賞金は1本30万円で、企業スポンサーです。 各場所15日間、幕下以下は7日目からで、幕内は毎日取り組みます。スケジュールは朝8時から序ノ口、午後2時頃から幕内、6時終了です。千秋楽(最終日)は優勝決定戦が可能で、13勝2敗同士の巴戦がドラマチックです。優勝は勝ち星最多で、複数なら決定戦、優勝額は1000万円プラストロフィーです。横綱は優勝義務のようなプレッシャーがあり、優勝回数は昇進基準にもなります。たとえば、白鵬の45回優勝は記録的です。スケジュール管理は協会が厳格で、力士の体調チェックやドーピング検査もあります。地方場所は移動が大変で、部屋ごと新幹線やバスを使い、現地適応が鍵です。興行的に、初日は土俵祭で神事からスタート、懸賞金は試合前に旗で掲げられ、企業PRになります。一本約62万円(力士取り分30万円)で、1場所数千本かかります。優勝パレードは千秋楽後で、優勝者がオープンカーでファンに感謝します。このスケジュールは力士の年間ルーチンで、場所間は巡業(地方興行)でファンサービスします。優勝の喜びは大きく、インタビューで故郷や親方に感謝を述べます。協会は天気や災害で延期対応も備え、安定運営です。こうした流れを知ることで、本場所の緊張感が伝わります。
観戦文化とメディア
相撲観戦は国技館の桟敷席(座布団)や椅子席で、弁当を食べながら楽しむ文化があります。満員時は1万人の熱気で、歓声や拍手が飛び交います。SNS時代に海外ファンも増え、グローバル化が進んでいます。 チケットは電話やネット予約で、桟敷は抽選人気です。観戦マナーは静粛で、土俵に物を投げない、携帯撮影禁止を守ります。メディアはNHKで中継され、視聴率10%超、解説者が技を詳述します。新聞や雑誌の番付予想も伝統で、ファンコミュニティ活発です。現代のSNS(XやInstagram)で力士が発信し、若者層拡大、海外ファン向け英語配信も増えました。たとえば、YouTubeのハイライト動画で世界中に広がります。興行収入はチケット・放送権・グッズで、協会財政の柱です。コロナ後、オンライン観戦が増え、VR体験も試験的です。文化的に、女性ファン多く、力士のイケメン人気やグッズ販売盛んです。地方場所は地域振興で、観光客誘致をしてます。この相撲文化は伝統継承として観戦を通じ、礼儀が学べる教育効果もあるというわけです。
体を柔らかくする方法|初心者向けストレッチ&ヨガで柔軟性UPの秘訣


